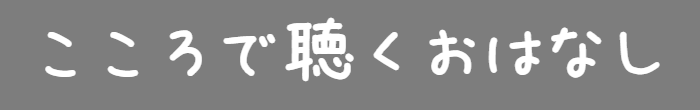小川洋子の「私のひきだし」その2
第3回「許すということ」

金光教放送センター
皆さま、おはようございます。作家の小川洋子です。『私のひきだし その2』、本日は第3回です。1回、2回と、金光教に関わる、学生時代と子ども時代の思い出を語りましたが、今日は視点を変えて、世の中の仕事、職業について少し考えてみたいと思います。
以前、女性誌のエッセイに、ホテルの朝食のルームサービスを運んでくれる女性について書いたことがあります。こちらはまだお化粧もせず、ほとんど寝間着姿だというのに、ホテルの女性はすでに完璧に身だしなみを整え、背筋をピンとのばし、笑顔を浮かべて朝食を運んでくれます。早朝からこうして働いている人がいる。てきぱきとプロの仕事ぶりを見せてくれる。そういう、働く人の美しさに心動かされた体験を描いたエッセイでした。
しばらくして、また別のホテルに宿泊し、ルームサービスを頼んだ時のことです。運んでくれた女性が、部屋を去り際、遠慮気味に言いました。
「私たちの仕事に目を留めてくださって、どうもありがとうございます」
女性は涙ぐみ、それからまたプロの笑顔を取り戻して、部屋を出て行きました。ほんの一瞬の出来事でした。
やはり、自分の見方は間違っていなかったのだ、と思いました。自分の仕事に誇りを持ち、地道に訓練を積み、とにかく一生懸命働いている人は、その職業が何であれ、尊敬されるべきなのです。ホテルマンたちへの気持ちが、エッセイをとおして一人の女性に伝わり、何かしらの励みになってくれたのだとしたら、これほどうれしいことはありません。
考えてみれば私は、小説を書く以外のほとんど全ての仕事をすることができません。ショベルカーを操作して土を掘り返したり、ケーキを焼いたり、テニスでセレナ・ウィリアムズを負かしたり、何もかもできないことだらけです。世の中は、自分にできないことをやってくれる誰かのおかげで成り立っているのです。
そう思えば、他人のミスも大目に見ることができる気がします。頭を下げてひたすら謝っている店員さんを前に、大きな声で文句を言っているお客さんを時折見かけますが、何があったにせよ、まずは許すところから始めたほうが、本人も気分がいいのではないでしょうか。怒る、という感情には、相当のエネルギーを使います。たとえ、相手が100%悪かったとしても、そのミスをなじるばかりでは、ただ疲れるだけです。
そんな時、ふっと心を鎮め、「この人には私に分からない苦労があるんだ。誰もミスがしたくてする人はいない。きっと何か事情があったに違いない。なのに、事情を説明する間も与えずに怒り散らしている自分のほうが恥ずかしくないか?」。そんなふうに思える心の余裕があれば、事はたいてい丸くおさまります。
しかしそう上手くはいかないのが世の常です。例えば私は芥川賞の選考委員をしているのですが、いいと思った作品の良さを説明するよりも、つまらないと思った作品の欠点を挙げるほうがずっと簡単です。「ここが良くない。ここも駄目」と言っているうちに、だんだん気分が高揚してくるのです。けれど文学賞の選考では、どの作品を落とすかではなく、「どの作品を受賞させるか」に主眼を置かなければ、充実した選考会にはなりません。一見、欠点のようであっても、それを非難する前に、許せる欠点であるかどうか、という視点でとらえるのです。
どのような作品であっても、それはやはり誰かが一字一字、時間をかけ、刻み付けるようにして記した小説です。同じ作家ならば、その労力がどれほどのものか、分からないはずはありません。この小説は、この人にしか書けないもの。自分には書けない小説。そう思えば、選考会に臨む態度も、おのずと定まってきます。
ですから、先に述べた、誰かに怒りをぶつけるような場面でも、非難ではなく、許しの気持ちを持つことができたら、どんなに楽でしょうか。相手は、自分にできない仕事をしている人である。そう思うだけで、尊敬の念を抱くことができます。相手に対して想像力を巡らせれば、あらゆる人々が、結局は一生懸命に生きているのだ、という実にシンプルな真理に行き着くことができます。
信仰心は、人間に対する、この想像力を育んでくれます。社会的な地位や、見た目や、学歴、などといった外側の余計な飾りを取り払い、目の前にいる人の本質を感じ取ることが、信心の稽古になります。人々は皆、神様によって愛おしく思われているのですから、当然、許すことができるはずなのです。
本日は以上です。では、また来週、よろしくお願いいたします。