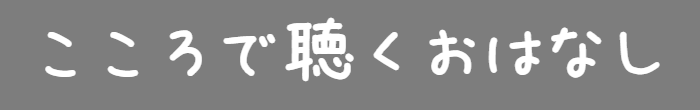●私の本棚から
「愛はふたたび」

兵庫県
金光教出石教会
大林誠 先生
おはようございます。兵庫県にあります金光教出石教会の大林誠です。
シリーズ「私の本棚から」。今朝は、昭和56年に刊行された『愛はふたたび』という本をご紹介します。
著者の平本行雄さんは、5歳の時に戦災孤児になり、以来、逆境が続いて、すさんだ生活に陥っていきました。しかし、中学3年生の時、そんな平本さんを、ある金光教の教会が家族のように温かく迎え入れ、高校にも通わせてくれたのです。この本はその実体験を小説風に書いたもの。一部を抜粋して読ませていただきます。
*
行雄は、最初は教会を裕福と思ったが、それは、これまで育った家に比べてのことであって、贅沢な暮らしではなかった。
他の人には、庠いところに手が届くようにお世話をされるのだが、ご家族の生活は実に質素なものであった。自分たちの楽しみというものがなく、旅行や観劇に行かれることもなかった。
「美味しいものを頂いたり、いい着物を着たり、温泉などに行くよりも、人様が喜んで下さることが、一番にうれしいことです」ということであったから、そういうことには見向きもなさらないのである。人間として、一般的な楽しみを捨ててまで人に尽くすことが、それ程に大切なことなのだろうか。行雄は自分が世話になっていることも忘れて、疑問に思うことばかりであった。
だが、そういうご家族の深い愛情も、行雄の心の硬い氷を溶かすには、一朝一夕にはいかなかったのである。
そうしたある日、行雄の心を大きく揺るがす出来事が起きた。いつものように遅い起床で二階から降りて行くと、この日に限って妙な雰囲気である。
「何かあったのですか?」
「うん、お母さんの手文庫が見当たらんらしいで……」
行雄はドキッとした。続いて嫌な予感が頭を走った。これまでも、こういうケースはしばしば経験している。何か物がなくなったりすると、次に起こることは疑われることである。
「もし疑われたり、尋ねられたりしたら教会を出て行こう」
行雄は心の中で決心を固め、教会の人たちの動向を見守った。
手文庫はついに見つからずに、盗られたという結論になった。金額はどうでもいいが、大切な書類なども入っているから、一応、警察に届けようということになった。
幸い信者さんの中に警察官の人がおられたので、奥様が電話で頼もうということになった。警察という言葉が嫌な思い出と共に、行雄に過去を蘇らせた。
「やっぱり俺は疑われてるんや。自分たちで聞くのが辛いんで警察に頼むんやな」
行雄は、やっぱり大人はいざとなると汚いと思った。
「疑うんなら疑え、後で犯人が分かって謝っても遅いで。こんな人間でも五分の魂は持ってるんや。金光教は邪教やと世間に出て宣伝したるわ」
自分が疑われていることを予測して、行雄は警官からの尋問があることを覚悟した。
「もしもし、あっ、Kさん、ちょっと調べてもらいたいことがあるんですけど……」
奥様の電話の声が、障子を通して聞こえてきた。行雄は、どういう会話になるか全神経を集中した。障子を隔ててはいたが、相手の声も微かに聞きとることができた。
「ああ奥さん、何か変わったことでもありましたか?」
「ええ、ちょっと手文庫が見当たらなくなって……」
紛失した時の情況説明や、何が入っていたかというようなことが縷々続いたが、説明を聞いたKさんは、次のように言った。
「よく分かりました。早速に行って調べてみますが、内部の事情に詳しい者の犯行ですなあ」
「というと?」
「いや奥さん、教会には、ほかの子供さんも居られますねえ?」
「ええ、あんたも知ってはる通り、ほかの子いうたら行雄さんのことになりますかねえ」
「あの子の過去のことは、もちろんご承知でしょうねえ」
「そら知ってますがな、それで?」
「いや詳しく調べてみないと分かりませんが、内部の人間がしたかも知れません」
「あんた、ようもそんなこと言いなさるな。そら以前のことは、わても少しは知ってまっせ。けど、いつまでもそんなこと思うてはったら困りますなあ。あの行雄さんを疑うてはるんでっか?」
「いえ、別に疑う訳ではおまへんが……」
「そういうふうに聞こえますがな。あんたも何年信心してはるの。私らがどういう思いで、あの子を育てているか分かってはりますか? あの子が怪しいやなんて、ようそんなことを……あの子はそんな子と違います」
「分かりました。そんならすぐ調べます」
電話は切れたが、行雄はそのまま動くことができなかった。
涙が目に滲んできて、前が見えなくなっていった。
「もう俺は、この先生や奥様について行こう。この金光教を信じて行こう。世界中の人が、『金光教は邪教だ。信じるな』と反対しても、教会の家族の人たちが信じておられる限り、この道について行こう。それに、どうすれば親先生や親奥様のようになれるのか、どうすれば、見も知らぬ人にでも深い愛を示していけるのか、それをじっくりと見届けよう」
行雄は、そう決心した。
※表記は原典に基づいています。
*
いかがでしたか。平本さんは、後に金光教教師となって、人助けに一生を捧げられました。自分は愛されているという実感が、いかに力強く人生を支えるか、また、生き方を変える力にもなるか、ということを、この本は教えてくれます。そして私も、教会を預かる一人の人間として、この教会の奥様のあり方に、襟を正される思いがするのです。