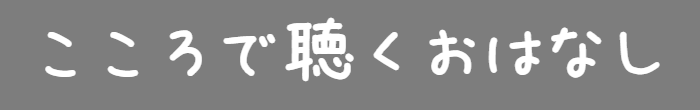●シリーズ「あなたへの手紙」
第1回「やる気のない息子/人は皆神の子?」

金光教放送センター
おはようございます。兵庫県・出石教会の大林誠です。
今日はまず、愛知県にお住まいの52歳の女性のお悩みです。
「私は夫を早く亡くし、夫婦で経営していたフラワーショップを一人で切り盛りしながら、一人息子を育ててきました。その子が一昨年ようやく大学を卒業し、「店を手伝う」と言って帰ってきたので、私はとてもうれしかったのですが、息子が張り切っていたのは最初の1カ月ぐらいで、今は昼ごろにやっと起きてくるという有り様です。早く仕事を覚えなければ、先々本人が困ることになるのですが、叱ると、「言われなくても分かってる」と反発するばかり。そんな息子が歯がゆくてたまりません。どうすれば息子がやる気を起こしてくれるでしょうか」
こんなお悩みです。
店の経営と子育てと、これまで本当に頑張ってこられたんですね。そのご苦労を間近に見ているからこそ、息子さんも、早く親孝行をしたいと思って帰ってこられたんでしょうね。優しいじゃないですか。そんな息子さんですから、きっとあなたの今の気持ちも、よく分かっていると思いますよ。
フラワーショップといえば、体力も知識もセンスも必要となる、大変なお仕事だろうと思います。それだけに、若くて元気なうちに色々と勉強しておかなければと、親からも言われ、本人も分かっていながら、それでも仕事に打ち込めない。甘えだと言ってしまえばそれまでですが、きっと息子さんも、今、自分自身の不甲斐なさを嘆いて、もがき苦しんでいるんじゃないでしょうか。
親としても、つらいですよね。子どものためを思って叱っているのに、かえって反発を招き、逆効果になる。となると、今はその心配を子どもに直接向けるのではなくて、神様に向けていく。心配を願いに変えて、祈りながら待つ。それしかないと思うんです。親心とは、切ないものですね。
神に願ってどうなるものか、とお思いかもしれません。でも、一心の願いには、神様は必ず応えて下さいます。
あなたとほぼ同年輩の女性で、息子さんとの関係で悩み、教会に参拝するようになった方がありましてね、この方は何度も参拝を重ね、神様の前で自分の心を見つめるうち、こうして悩んでいるのは、子どもがこの上なく愛しいからだ。そんな子どもを神様から頂いているのだと、我が身の幸せに気付かれたのです。やがて、息子に感謝する気持ちまで湧いてきて、そこから、もつれていた親子関係が次第にほぐれていきました。
元々は、息子が変わってくれますようにと願ってお参りされたんですけれども、思い掛けないことに、信心によってまず自分自身が変わったんですね。それが助かりへの糸口になりました。
あなたの願いに、神様はどう応えて下さるか。それを楽しみにしながら、金光教の教会を訪ねてみて下さい。
次は、東京都にお住まいの45歳の男性から頂いたご質問です。
「近年、世界各地でテロが起こり、国内でも凶悪犯罪が後を絶ちません。ところが金光教のラジオ放送では、「人はみな神の子」などとのんきなことを言っています。そんな奇麗事では済まされないのが現実ではないでしょうか」
このようなご質問です。
ラジオ放送を通して金光教の教えを覚えていて下さったんですね。ありがとうございます。
おっしゃる通り、金光教では、「人はみな神の子」だと教えられています。そして、人と仲良くしたい、優しくしたいという「良い心」も、神様から授けられてこの世に生まれてきたと考えています。
もちろん、世の中には鬼のような心の人もないとは言えません。でも赤ちゃんの時から悪人であるような人はいませんから、きっと何か訳があって、不幸にも、その良い心が閉ざされてしまっているに違いない。
どんなにひどいことをする人を見ても、「この人に一体何があったのだろうか。もしかしたら自分も、境遇によってはそうなっていたかもしれない」と想像する心の余地を失ってはならないと思うのです。
殊に今は、人間に対する信頼や安心感が揺らいでいる時代です。不確かな情報が飛び交い、多くの人々が一気に憎しみを燃え上がらせて、戦争にさえ突入してしまいかねない、危険な時代でもあります。そんな時代だからこそなおさら、一時的な感情に惑わされず、奇麗事と片付けず、「神の子」としてどこまでも人を尊ぶ態度が、ますます大切になっていると思うのです。
金光教の教祖は、ある人に、「日に日に悪い心を持つなよ。人に悪いことを言われても、根に持ってはいけない」と話したことがありました。その人が、「それでも、向こうが悪い心を持って来れば悪い心になります」と口答えすると、「それでも、悪い心を持ってはいけない」と諭したとのことです。
悪いことをされたら仕返しをしたくなるのが人情。しかし、それを克服出来なければ、争いの連鎖を断ち切ることは出来ません。相手の「悪い心」に惑わされない「それでも良い心を」という決意を、一人ひとりがどこまで持ち続けられるか。世界の平和はそこに懸かっていると私は思います。