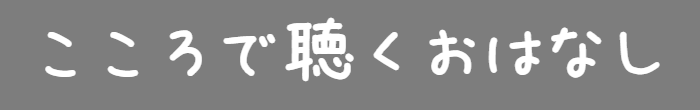●信者さんのおはなし
「あの言葉がなかったら」

金光教放送センター
京都三条通に和紙工芸品の卸問屋、「長谷川松寿堂」があります。「松」に「寿」と書く松寿堂です。
ショールームには、和紙で作った色とりどりのびょうぶや扇子、便せん、中にはモダンなデザインの小物入れなど、どれも手に取ってみたくなるものばかりです。案内して下さったのは、その松寿堂の2代目の奥様、長谷川敏子さん。現在は敏子さんのご長男が社長となって、さらに展開している老舗です。
敏子さんは今年89歳、美しい京都弁が似合うステキなおばあちゃんです。「昔は色紙と短冊しかあらしまへんでしたんえ」と、敏子さんは昔を懐かしむように言葉をつなぎます。「こんなええ場所に、店が出来ましたのは先代のおかげどす。先代は丁稚から、えらい苦労しはった方どした」。
長谷川松寿堂の初代、長谷川忠三さんは敏子さんのおしゅうとさんに当たりますが、熱心に金光教の信心をしておられました。
そのご縁で、敏子さん夫婦は金光教加茂川教会で結婚式を挙げました。その時が敏子さんと金光教の初めての出会いでした。
お父さんは朝参りを、お母さんは夕方にお参りと、熱心に信心をしていた家族でしたが、敏子さんに信心を強制することはありませんでした。
でも、ある日のこと。お父さんは京都四條南座の芝居の券を敏子さんに下さいました。南座は教会の近くにあるので、「敏子、芝居を観ておいで。その帰りにちょっと教会に参っておいで」と言われました。久しぶりの芝居を楽しみ、教会に行って先生にあいさつをして帰ってくるとお父さんは、「よぉ、よぉ参ってきたなぁ」と、何度も褒めて下さるのです。こんなに喜んでもらえるのなら、自分からお参りしてきたら、どんなに喜んでもらえるだろうかと、敏子さんは知らないうちに自分からお参りするようになっていきました。
敏子さんのご主人は8人兄弟の長男。しかも戦争でご主人を亡くしたお姉さんが、子ども2人を連れて戻ってきており、大家族の大変さがありました。それでもお母さんは、「敏子も遠慮せんと、たくさん子どもを産みや」と言って下さり、自らねんねこを着て、敏子さんの4人の子どもたちの世話をして下さいました。一代で大変な苦労をして立派な店を構え、財産をこしらえたのに、ちっとも偉ぶらずに世話をしてくれるお母さんに触れながら、信心のある家に嫁いできて良かったと敏子さんは思ったのでした。
また、お父さんは、「人間というものはお互いに助けおうて生きるんやで。助けといたら、必ず助けてくれる時があるからな」と、敏子さんのそばにそっと来ては、ぽつぽつと何気なくおっしゃるのでした。そんなふうに語りかけてくれるお父さんの言葉が、敏子さんは大好きでした。
ところが、子どもたちが大きくなって、兄弟たちも結婚して外に出たころ、お母さんが脳卒中で倒れました。
金光教の教会には、ただお祈りをする場だけでなく、お結界と言って、先生に願い事や困ったことなどを聞いていただく場があります。そこへ敏子さんは行って、「お母さんはいつも脳卒中にはなりたくない、と言うてはりましたのに、脳卒中で倒れてしまわれました」と夢中で先生にお話ししました。すると先生は、「あんたのお母さんは偉い人なんやで。それはあんたに徳を積ませるためなんや。そのためにお母さんは体を傷めてくれはったんやと思うて、大事にお世話をするんやで」とおっしゃったのです。徳を積むということの意味は分かりませんでしたが、その言葉を敏子さんはしっかりと心に刻みこみました。
幸い、家にはお姉さんがいてくれたので、2人でお世話をすることが出来ました。お父さんがいつも、「人を助けといたら、必ず助けてくれる時がある」と言われたのは、このことだったと思いました。それから、お姉さんと助け合って、一生懸命にお母さんのお世話をいたしました。
そして6年半の介護の後、お母さんは亡くなりました。その時も敏子さんはすぐに教会に参拝しましたが、その時、先生は、「あんたな、お母さんはつい立てやったんやで。あんたと兄弟たちとの間に立って、あんたを守ってくれてはったんや。そのつい立てが無くなって、これからはあんたが顔を出すんやで。お母さんのお世話をしていた時と同じようにしておりや。私が、してきたということが一切ないように」ときつい口調で言われました。
慰めの言葉でも、ねぎらいの言葉でもなく、「分かったか。お母さんはつい立てやったんやで」という意外な言葉は、そのきつい口調のせいもあって、その時の敏子さんには厳しく響きました。
敏子さんは思わず涙がこぼれ、家に帰ってしまおうかと思いました。ところがその時、厳しい顔付きの先生の目にも涙が光っていたのです。その涙を見て、敏子さんは先生の深い思いを悟りました。
お母さんが病気になった時も、亡くなった時も、先生は大家族の長谷川の家での敏子さんの立場を心配して下さっていたのでした。
何十年経った今も、改めて敏子さんは思います。
「あんたに徳を積ませるためやで。そう思うて大事にお世話をするんやで」「お母さんはつい立てやったんやで」という、先生の言葉がなかったら、私はこの家で辛抱が出来ただろうかと。そして、こうして先代からの精神そのままに息子が商売を継いでくれ、家族に大切にされている自分を思う時、これは自分の力で出来たのではない、これこそが「徳」というものであろうと、先生の祈りの深さを思うのです。