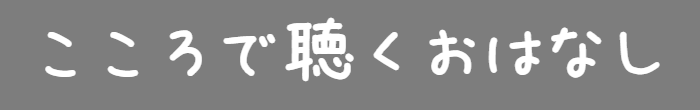●平和
「灯りのともる暮らし」

金光教大美野教会
阿部惠一 先生
今から68年前、京都に在住していた私は大学に入学するや間もなく、学徒勤労動員令により、日本海に面する京都府与謝郡にあった軍需工場で働くことになりました。
ここは、日本海軍の航空機の整備、修理や生産を担う所でした。近くにある天橋立の風光明媚な場所を訪れる余裕などはなく、過酷な労働条件の中、私の仕事は、ひたすら山に入り穴を掘る、防空壕を掘ることでした。作業は班で行動しますので、一人でも集合時間に遅れたり、ちょっとしたミスをすると、連帯責任として、「両足を開け、歯を食いしばれ!」と、班全員が平手打ちされることもありました。
しかし、私たちの指揮官は、いつも、「青春は意気込みであり、熱であり、顧みる時のほほ笑みである」という言葉を掛けてくれました。青春を謳歌するなど想像も出来ない当時、「青春」という言葉を聞くことは、今考えてもまれであった思いますが、絶えず学生であった私たちに希望を失うなと言われているようにも感じました。
やがて月日過ぎて8月15日、正午前に全員集合の命令を受け、工場にいる全員が、暑い炎天下の広場に集められました。直立不動の姿勢をとらされて待機していると、前方の机の上に置かれたラジオから聞こえる雑音混じりの声、何の放送か分からぬまま終わりました。
夕方近くになって肩を抱き合って泣いている女子学生の姿、ラジオを通じての声は、後に玉音放送と言われた天皇陛下の声でした。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び…」と言われた戦争の終結、敗戦を告げられたお言葉でした。
この放送の後、ソ連軍が上陸してくるかも知れないなどの噂が流れ、工場内は騒然となり、広場では人が近寄らぬように銃剣を持った兵士が見守る中で、書類などを消却していました。徴用令によって工場で働かされていた人たちの中には、資材が納めてある倉庫に無断で押し入り、食料や衣類など、持てるだけの品物を盗んでいく人もいました。
私たちが工場を退去する時、私たちの指揮官は、「これからは君たちの時代が来るだろうが、体に気を付けて勉学に励むように」と、敗戦後、この先どうなるかも分からぬご時勢でしたので、これが今生の別れとなるやも知れぬ思いからか、泣きながら私たち一人ひとりの手を握り、励まして下さったことは、今も大切な思い出の一つです。
友人たちと帰郷するために最寄りの駅へ行き、乗車券を買い求めようとしましたが、駅員からは工場から指示がないので、乗車券の発売は出来ない、とのことでした。結局乗車券は買えず、友人と相談して、隣の駅まで行こうということになり、各自が所持品を入れたリュックを背負い、支給された転出証明書と乾パン1袋を受け取り、夜の8時ごろ、寮を出発することにしました。
暗い山道を歩き続け、峠を越えて、ようやく明け方、宮津駅に着きました。今でこそ、2時間ほどで帰ることが出来ますが、その時は、列車の乗車券の発売にも、遠距離に制限があり、京都市内へ帰るにも2度乗り継ぎ、支給された乾パンを食べ、水を飲みつつ、19日の夜、まる一日を費やして、ようやく自宅にたどり着きました。
家族宛てに出すはがきも当時は検閲があり、余計な情報が漏れないように、差し障りがあると判断されればその箇所を墨で消されていましたので、突然の帰宅に家族は驚きましたが、お互いに無事であったことを抱き合いながら喜び合いました。京都市内は大きな戦禍は免れたとはいえ、数回にわたる空襲に遭い、尊い多くの命が失われました。
戦争が終わり、灯りが外に漏れないようにする夜の灯火管制もなく、少しは町の様子も明るくなったようでしたが、それでもまだ各家では、電力制限を強いられ、停電時にはろうそくの灯りに頼る日が続きました。
戦後の食料不足、物資の欠乏の生活、学校へ登校しても授業を担当される教授が栄養失調のため休校となることもあり、私たちも体力不足、栄養不足から免れることは出来ませんでした。
その後、京都市内に米軍が進駐する事態となり、各家では出入口を閉ざし、町の不気味な静けさの中を銃を持った兵士が巡回し、夜ともなれば各家庭の暗さに比して、米軍に強制的に取り上げられた建物は、不夜城のごとく灯りがこうこうと輝き、暗がりの中に浮かんで見えました。
資源の乏しい国が資源を手に入れようと、戦場の拡大にもつながったのでしょうが、一般国民は、戦局の事実を知らされず、敗戦となれば、明日の日を、いや、今日を生きるために、各自が工夫、努力して生きていたように思います。
今もなお日々の新聞記事、報道される話の中に、国と国が争い、尊い命が失われています。
金光教の教祖様は、「人が人を助けるのが人間である」と教えておられます。私たちは到底一人では生きられないのはもちろんでありますが、人の間と書く人間という文字を見た時、私たちは、常に人と人との間にあってこそ生きていられるのが事実かと思います。
他の人との関係なくしては生きていくことが出来ず、この関係の中に、いつも穏やかに、生きている、いや、生かされている喜びを失わず、お互いが努力し合い、助け合いながら、平和な世の中を築いていく大切さを痛感しています。今日を喜び、明日を楽しむ生活を築くためにも、灯りのともる日々の暮らしに、今、「ありがとうございます」とお礼を申さずにはおれないのです。