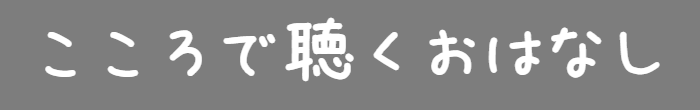●信者さんのおはなし
「お邪魔にならない生き方をなさい」

金光教放送センター
横山和光さんは、陶磁器で有名な、愛知県瀬戸市に生まれ育ちました。
時は昭和32年の春、当時16歳だった横山さんは、病の抜けきらないフラフラの体で、母親に伴われ、初めて金光教瀬戸教会の門をくぐりました。
その1年前、彼は厳しい受験競争を勝ち抜いて、ある名門高校に進学し、張り切って勉強を始めました。ところがそのわずか1カ月後に、胸膜炎になってしまったのです。長期間の安静が必要となり、学校に休学届を出して、自宅や病院で療養しましたが、体がスッキリしないまま、早くも次の春がやってきたのでした。横山さんは不安と焦りに押し潰されそうでした。お母さんが教会に連れて行ってくれたのは、そんな時のことだったのです。
教会の先生は、信者さんたちから、「親先生」「親奥様」と呼ばれて慕われている70代のご夫婦でした。お2人は初対面とは思えないほど親しく温かく迎え入れてくださり、真剣に話を聞き、神様に一緒にお祈りしてくださいました。
特に横山さんの心を動かしたのは、親奥様の優しくも力強い励ましの言葉でした。
「神様におすがりしていれば必ず助けていただけます。私も一生懸命お願い致しますから、しっかり信心して、おかげを受けてください」
彼はこの時、ここで信心を教えてもらい、助けていただこうと決意したのです。
高校には退学届を出し、しばらくは自宅で安静を保ちました。次に、体力を付けるために、教会の近くの工場で体に合う仕事をもらいました。仕事帰りには教会にお参りし、親奥様と話をします。親奥様は、信心に基づく生活の仕方について、事細かに教えてくださいました。
この中で何度もおっしゃったのは、
「お邪魔にならない生き方をなさい」
ということでした。
若者に向けた言葉にしては、少し消極的な感じもしますが、おそらくこれは、一つには、まだ体の調子が整わない横山さんに対する心遣いでもあったのでしょう。焦って無理をしてはいけない。今は身近なところから、細やかな心配りをする稽古をなさい。そんな意味で言われたのではないでしょうか。
また一つには、自分の力を過信していると、役に立つつもりが、かえって迷惑になることもある。どこまでも人の立場を思いやる謙虚な生き方をしていくようにと、促されたのではないでしょうか。
「お便所でも銭湯でも、履き物が脱ぎ散らかしてあったら、他の人の履き物もそろえてあげるんですよ」
そんな親奥様の話を聞きながら、横山さんは、「なるほど、信心する人は、こういう丁寧な心配りをしていくんだな」と、ストンと腑に落ちる気がしました。
ようやく体力が回復し、改めて高校に入り直したのは、20歳になってからのことでした。読書が好きで、図書館で仕事をすることにあこがれていた彼は、この夢に向けて、働きながら定時制高校に通うことにしたのです。
彼の周りの人々は、できる限りの協力を惜しみませんでした。ある人は、家で無理なく働けるようにと、良い内職をあっせんしてくれました。また近所のある人は、「それよりうちの工場に来なさい」と言って働かせてくれ、通学には、自分のスクーターを貸してくれました。4年間の定時制高校を終えた後は、夜間の短期大学に進みましたが、その時にも、ある会社が雇い入れ、大学に通いやすいよう配慮してくれました。
横山さんは在学中に図書館司書の講習を受け、同じ大学の図書館に正規採用されました。勤めていた会社の方々も、彼の努力が実ったことを喜び、快く送り出してくれました。こうして同じ大学で勉強も仕事もすることができたのです。
このように、多くの人が味方になってくれたのも、横山さんの誠実さが広く信用を得たからに他なりません。親奥様の教えのとおり、誰も見ていない所でも人のために真心を尽くし、心配りを行き届かせる生き方が、人々の心を動かしたのです。
この生き方は、図書館での仕事の上にも貫かれました。欲しい本が貸し出し中になっていて、がっかりしている学生たちには、「どんなことを調べたいの? じゃあ、この本はどうかな。同じことが違った角度から書かれていて、いい勉強になるよ」と、丁寧にアドバイスをします。学生にとって横山さんは、実に頼もしく、ありがたい存在でした。卒業生たちから、「この大学で一番楽しかったのは、図書館で勉強させてもらったことだ」とお礼の便りが届くこともありました。
こうした実直な働きぶりが認められ、やがてその図書館の責任者となり、図書館関連の様々な全国組織の中でも、頼られる存在となっていったのです。
横山さんの仕事上のモットーは「潤滑油になる」ということでした。自分1人でできることなど何もない。自分の務めは、職員の仕事や、学生の皆さんの勉強がスムーズにできるよう、お世話をさせていただくことだと言うのです。この謙虚さも親奥様の教えからきているのでしょう。
社会人としてのスタートは人より数年遅れましたが、教会で信心を教えていただいた青年時代は、その後の人生の土台を築く、とても大切な時間となりました。
退職後も、町内会のお世話や、教会のさまざまな活動に心を込めて取り組む横山さん。そのまぶたの裏には、「お邪魔にならない生き方をなさい」と導いてくださった、在りし日の親奥様の優しい笑顔が今も映っているのです。