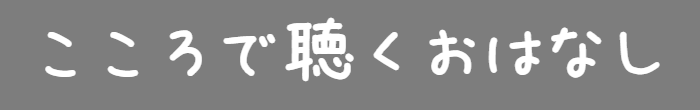●こころの散歩道
「お世話になります」

金光教放送センター
妻の実家に帰省していたある日のことでした。外からダッダッダッと大きな音がしてきました。窓からのぞいてみると、コンバインが稲刈りをしています。働く車が大好きな小学2年生の長男が外へ飛び出していきました。お隣の田んぼが稲刈りを始めたのです。
それまで稲刈りを見たことのなかった私は、「まだ秋も深くないこんな時期に稲刈りをするんだな。稲はもう色付いていたのかな」とぼんやり想像を巡らせていました。
一方息子は、目を輝かせてその様子を眺めていました。ひとしきり見学して帰ってくると、何かを思い付いたように私に話し出してくれました。「そういえば、教科書にお米の出来るまでが載っていたよ」。「じゃあ、明日家に戻ったら教科書を見てみよう」。
翌日、家に戻った息子は、早速教科書を広げ、苗作りからコンバインを使って刈り取るまで、さらには白米になるまでの米作りの大変さを私に教えてくれました。そして、「いっつもおいしくお腹いっぱい食べているご飯がこんなふうに出来てくるなんて知らなかった。感謝しなくっちゃね」とうれしそうにほほ笑んでいました。その笑顔に、いつも食べているご飯に、こんなにも多くの人が関わっているんだと知った驚きと、そこに湧き上がってきた息子の純粋な感謝の気持ちを見るのでした。
ある方がこんな話をしてくれました。
「私は、長年、ボランティアで炊き出しに参加してきました。月に1回、ボランティア仲間でおにぎりと豚汁などの汁物を作り、配るんです。最初は、私自身料理もあまりできないし、量も多いので、大変だなという思いがずっとありました。でも、参加を重ね、慣れてきたこともあるのでしょうか。やりがいを感じてきました。もちろん、集まっている皆さんのこれまでのことも知らないし、これからのことを祈らずにはいられないけれど、料理を手渡している今、この時、少しでも皆さんの役に立てていたらいいなと思いました。それからは、ずっとそのように思っていたんですが、最近気付いたんです。私は人助けをしているんだと思ってきましたし、そのことにやりがいも感じていました。でも、違ったんです。炊き出しをしても、受け取ってもらえなければ渡せない。料理を振る舞うにも、食べてもらえなければどうしようもないと気付いたのです。その時からは、受け取ってくれてありがとうと思えてくるようになりました」。
このようなお話を聞かせてもらいました。
私は、「支える人が実は支えられていた」「助ける人が助けられていた」「そんなこともあるんだ」と思わされたのでした。
3年間の介護生活を経てお母さんを看取った一人息子さんのお話です。
その方は、「介護の最中は体力的につらい。睡眠が満足に取れない。仕事との両立が難しい」とおっしゃっていました。しかし、そんな生活が続いていく中、ある時、「介護できるというのは、親孝行のチャンスをもらっているのだなとだんだん感じるようになってきたんです」と教えてくれました。「介護と仕事の生活は、大変なことが多いには違いないけれど、母との時間の過ごし方を大切に思えるように今はなっているんです」ということでした。立派な方だなあと思いました。
そして、介護の日々が終わりました。いろいろと振り返ったのでしょう。数カ月の後、こんなことをおっしゃいました。
「介護できることを親孝行のチャンスと思えたことを、我ながらよくそう思えたなと多少は自負していたところもあるんです。でもね、よくよく振り返ると、私が思えたというより、そう思わせてくれるような母だったんですよね。ほんとにありがたい親をもって幸せ者だったんですよね」。
そうしみじみと話してくれました。
今日紹介したお話は、どれも当然のように思っていた物事の背景がふいに見えたことがきっかけとなった、心からの純粋な感謝の気持ちがありました。
そして、こんな気付きが一緒にあるように感じます。それは、支え、支えられている、支え合いの中に生きていること。当然ではありながら、とても大切なことが見えなくなっていたなという、そんな思いです。
それぞれの素直で純粋な感謝の気持ちに触れ、私ももうちょっと丁寧な生活を心がけて、日常の中に潜んでいる大切なことを見過ごしてしまわないように、そして、生活の中に見つけた大切なことへの感謝の心を育てていきたいと思うのでした。